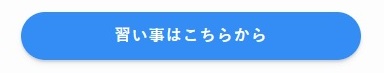How to Paint a Red squirrel with Watercolors/art.jp.net
ここに掲載されている透明水彩画は、Anna Masonのオンラインスクールが提供する
写真を使用して制作された細密画です。Miniature painting.
The transparent watercolor paintings shown here are
miniature paintings created using photographs provided by Anna Mason’s online school.
赤リスを水彩で描いてみました
I tried to draw a Red squirrel in miniature.
「アカリスはヨーロッパやアジアではよく見られますが、ここイギリスでは今ではめったに見られなくなりました。さび色のふわふわのキャラクターを見つけたときは、本当にうれしいです。
この絵には捉えるべき細部が膨大にあるため、大規模な作業が非常に役立つことがわかります。私は約14 x 18インチ(36cm x 45cm)で私のものを描きました. そのスケールでも、細かなディテールをペイントするには、ten-zero ブラシを使用する必要がありました。塗装が完了するまでには時間がかかりますが、詳細を簡単に塗装できるように、私よりもさらに大きく作業することができます.
長い毛皮や短い毛皮など、キャプチャするビジュアル テクスチャがいくつかあります。順を追って説明します。つまり、このチュートリアルは長いです。ですから、これをプロジェクトとして見て、時間をかけて、この愛らしい森の生き物の素晴らしい細部を観察して楽しんでください。」Anna
“Red squirrels are common in Europe and Asia, but are now rare here in the UK, so it’s a real treat when you spot one of these fluffy rust-coloured characters.
There is a huge amount of detail in this painting to capture, so working on a large scale proves to be very helpful. I painted mine at about 14 x 18 inches (36cm x 45cm). Even at that scale, I had to use a ten-zero brush to paint the fine details. It will take a while to finish painting, but you can work even larger than I can so that you can easily paint the details.
There are several visual textures to capture, including long fur and short fur. I will explain step by step. That said, this tutorial is long. So, look at this as a project and take your time to observe and enjoy the wonderful details of this adorable woodland creature. ”Anna
Draw an illustration of a red squirrel. Watercolor painting of squirrel
赤リスのイラストを描きます。りすの水彩画

赤リスのイラストは5~6分で全体像だけ描きます。
あまり濃くならないよう心掛けましたが、すこし力が入ってしまいました。
The illustration of the red squirrel takes 5 to 6 minutes to draw just the overall image. I tried not to make it too dark, but it ended up being a bit strong.
Undercoat the red squirrel
赤リスの下塗りをします

りすのBODYの基本となる色を全体に塗ります。
3日かかりました。
Paint the entire body with the basic color of the squirrel’s body. It took 3 days.
Squirrel watercolor painting day 5
りすの水彩画 5日目

5日目は、暗い部分の下塗りです。
On the fifth day, prime the dark areas.
Squirrel watercolor painting day 6
りすの水彩画 6日目

目を描くのに悩みぬいて進まず・・2日目になんとか彩色しました。
I was having trouble drawing the eyes and couldn’t make any progress, but I managed to color them on the second day.
Squirrel watercolor painting day 7
りすの水彩画 7日目

色の濃い部分の毛並みを塗ります
Paint the dark areas of the fur
Squirrel watercolor painting day 8
りすの水彩画 8日目

胴体の彩色に入りました。
I started coloring the body.
Squirrel watercolor painting day 9
りすの水彩画 9日目

胴体の下塗りは雌雄利用しました。いよいよ顔の下塗りに入りました・・
I used male and female undercoating for the body. I’ve finally started applying the undercoating to my face…
Squirrel watercolor painting day 11
りすの水彩画 11日目

11日目かおの彩色に入りました。ミリ単位の作業になります・・・
On the 11th day, I started coloring Kao. It will be a millimeter work…
Squirrel watercolor painting day 14
りすの水彩画 14日目

14日目 顔の彩色が
終わりました。リスの可愛らしさを表現します。
Day 14: Coloring of the face it’s over. Expresses the cuteness of squirrels.
Squirrel watercolor painting day 18
りすの水彩画 18日目

かわいいりすの尻尾に取り掛かりました・・・
I started working on the cute squirrel’s tail…
Squirrel watercolor painting day 22
りすの水彩画 22日目

りすの 顔に取り掛かりました・・かなり時間がかかりそうです
I started working on Squirrel’s face…it looks like it will take quite a while.
Squirrel watercolor painting 24th day finishing
りすの水彩画 24日目 仕上げ

りすの髭 全体を整えて仕上げました。
The entire beard of the squirrel was trimmed and finished.
赤リス(Sciurus vulgaris)は、ネズミ目(Rodentia)に属する哺乳動物で、一般的にリス(squirrel)として知られています。赤リスはユーラシア大陸および北アフリカに広く分布し、特にヨーロッパとアジアの森林地域で見かけられます。
- 外見: 赤リスは小型の哺乳動物で、体長は約20〜25センチメートルで、尾は約15〜20センチメートルあります。その体は灰色から赤褐色で、耳は立ち耳で毛皮は柔らかく密集しています。特に耳の周りには房毛(飾り毛)があります。
- 食事: 赤リスは主に樹上性で、果物、木の実、種子、花、昆虫、鳥の卵などを食べます。彼らは広い食物幅を持ち、季節や生息地に応じてさまざまな食べ物を探します。
- 生息地: 赤リスは広範な生息地に適応し、森林、公園、庭園、都市部などで見かけられます。特に庭園や公園では人間によって提供される餌や食物を探して生活することが多いです。
- 姿勢と行動: 赤リスは木に住み、木の枝や幹を巧みに走り回ります。また、彼らは尾をバランスをとるために利用し、ジャンプや飛び移りを行います。特に食物を探すために木々に登り、鳥の巣や樹洞を訪れることがあります。
- 繁殖: 赤リスは通常、春と夏に繁殖します。妊娠期間は約3週間で、産まれた子リスは母親によって育てられます。
The red squirrel (Sciurus vulgaris), commonly known as a squirrel, is a mammal belonging to the order Rodentia. Red squirrels are widespread across Eurasia and North Africa, and are especially found in forested areas of Europe and Asia.
Appearance: Red squirrels are small mammals, about 20-25 centimeters long, with a tail about 15-20 centimeters long. Its body is gray to reddish brown, its ears are upright, and its fur is soft and dense. There are tufts of hair, especially around the ears.
Diet: Red squirrels are primarily arboreal, feeding on fruits, nuts, seeds, flowers, insects, and bird eggs. They have a wide food range and seek out different foods depending on the season and habitat.
Habitat: Red squirrels are adapted to a wide range of habitats and can be found in forests, parks, gardens, and urban areas. They often forage for food and food provided by humans, especially in gardens and parks.
Posture and Behavior: Red squirrels live in trees and skilfully scurry around tree branches and trunks. They also use their tails for balance and for jumping and hopping. They may climb trees and visit bird nests and tree cavities, especially in search of food.
Breeding: Red squirrels typically breed in the spring and summer. The gestation period is about three weeks, and the baby squirrels are raised by their mother.